パート1で述べたように、これまでの精神分析理論では、思春期は、第二次性徴の始まりと共に性欲動の抑圧が難しくなり、エディプス・コンプレックスを焦点とする不安や葛藤が強くなる点で理解されてきた。思春期に発症する対人恐怖関連の様々な神経症症状もそうした点で理解が試みられてきた。しかしながら、思春期にはまた別の側面が存在する。発達心理学者のピアジェは、子どもの知的発達において、学童期に大きな変化が生じることを指摘している。具体的操作期から形式的操作期への移行である。有名な例は、太くて短いコップと、細長いコップに同じ量の水を入れると、太い方は水が入っている高さは短く、細長い方は長くなる。小学校の中学年くらい前の子どもは、「どちらにたくさん水が入っていますか?」と尋ねると、たいてい細長い方を指す。しかし、高学年になると、両者が変わらないことを理解することができる。つまり、「水の量」という概念を持つことができ、それはコップの形が変わっても変わらないことを理解することができる。
子どもは、思春期の手前に来ると、こうした形式的操作的認知が可能になる。子どもは、身近な人や集まりだけでなく、「○○市」、「○○県」、「国」、学校、家族などの様々な組織や集団のカテゴリーが理解できるようになる。そして、自分が属する様々な集団の違いも明確に理解するようになる。学校、家族、クラブ、町内会、親戚、塾など、である。とともに、それぞれの集団にいながら変わらない「自分」というものを明確にとらえられるようになる。そして、父や母という概念も明確になるとともに、人としての母や父も明確に意識できるようになる。まわりの友達や同級生も同様である。
もちろんそれまでも自意識と言われるものは育ってきている。特に、小学校3年生か4年生頃にそれはかなり明確になる経験を多くの子どもはする。初めて、親に秘密と持ち始めた時と重なることが多い。「親に言わなければ親はそれはわからない」、つまり自分だけが知っていることは、親と自分が別々の存在であること、そしてその流れで、自分というのは全く一人ぼっちであることを明確に意識する。
8,9歳ころに、多くの子どもはこうした自意識を持つようになるが、普段の生活の中でそれを明確に意識することはあまりなく、親子関係や友達関係などでも同様である。思春期に起こる「自意識革命」は、こうした部分的なものではなく、全面的なものである点にその衝撃の大きさが表れる。しばしば、それは、同級生とのトラブルという形で現れる。それまで友達だった子たちに仲間外れにされた、突然無視されるようになった、というものである。この流れの中に、「人の視線が怖い」「人から匂う、臭いと思われているのではないか」「顔が不細工と思われているのではないか」「自分の噂をしているのではないか」など、対人恐怖と関連付けられる様々な神経症的症状が現れる。
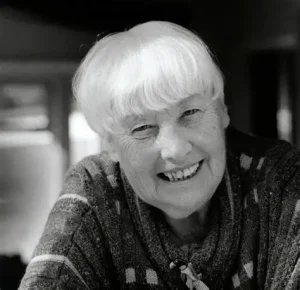 自閉症を持つ子どもとの精神分析実践をした精神分析家のフランセス・タスティンは、自閉症の子どもは、母親と自分が異なる存在出るという意識が育まれていないことに注目した。そして、そうした子どもと親との間では、彼女が付着的一体性と呼ぶ関係性がみられる。付着的一体性とは、子どもと親が、別々ではなく、身体的にもくっついている(付着している)という状態である。勿論、客観的に見ればそうした現実はない。タスティンが述べている状態は、自意識、そして他者意識が芽生えていない状態のことを指しているのである。こうした子どもは、母親が自分の体の一部ではないことに気づくことは、そうした子どもの対処能力を超えてしまう衝撃であるという意味で、トラウマ的であるとタスティンは述べている。
自閉症を持つ子どもとの精神分析実践をした精神分析家のフランセス・タスティンは、自閉症の子どもは、母親と自分が異なる存在出るという意識が育まれていないことに注目した。そして、そうした子どもと親との間では、彼女が付着的一体性と呼ぶ関係性がみられる。付着的一体性とは、子どもと親が、別々ではなく、身体的にもくっついている(付着している)という状態である。勿論、客観的に見ればそうした現実はない。タスティンが述べている状態は、自意識、そして他者意識が芽生えていない状態のことを指しているのである。こうした子どもは、母親が自分の体の一部ではないことに気づくことは、そうした子どもの対処能力を超えてしまう衝撃であるという意味で、トラウマ的であるとタスティンは述べている。
タスティンの述べていることは、多くの読者にとって一読しても奇想天外な議論としか取れないところがあるが、よく考えてみると、「自意識」というものは、他者ところなる自分を意識することなのである。つまり、自意識が立ち上がる前は、他者も自己も区別のない、一体性の状態なのである。
タスティンは、この付着一体性を、自閉症に特有の状態であるかのように書いたり、また実際そのように多くの読者に読まれてきたが、私は、こうした関係性なり方は、日本社会における多くの家族関係の特徴ではないかと考える。一見、子どもを自分とは異なる一人の人間であると認めたことを話す親御さんが、実際に振る舞いをよく見ると、自分の一部のように感じていることは臨床でしばしば経験する。そうした場合、子どもの方も、自分という明確な意識をもてない部分があり、そうした子どもの話しは主語が曖昧かわかりにくい、もしくは母親や父親とごっちゃになっている場合が多い。
さて、思春期になると先に述べた形式的操作期的知能が発達し、「自分」という意識が他者への気づき、関係性の基層にある付着的一体性を維持することが困難になる。そして分離性の気づき、自慰岸の立ち上がりはしばしばトラウマ性を帯び、その表れが様々な対人恐怖症的な症状ではないかと思われる。
タスティンは、分離性の気づきはトラウマ的になると述べているが、それは「赤ん坊の巣」」空想という形をとりやすいとも論じている。赤ん坊の巣空想とは、母親の体の中は、恐ろしい敵対者の赤ん坊で一杯だという空想である。これも突拍子もない考えの用であるが、漠然と教室に入るのが怖いという思春期の子どもの不安の背景として私の中では説得力のある考えである。教室の中=母親の体、他の生徒=敵対的な赤ん坊と理解できる。
このように、思春期に起こる対人恐怖関連の症状の多くは、それまで付着的な関係性、すなわち自他の未分化な関係性のなかにいた子どもが、突如、自意識に目覚めてしまうという衝撃と関連付けて理解できるように思われる。日本社会の多くの家族がそうした関係性を持っていること、そして同時に西洋的な文化洋式を「社会人」として要求されているという矛盾の中で起こる苦しみであるといえるかもしれない。